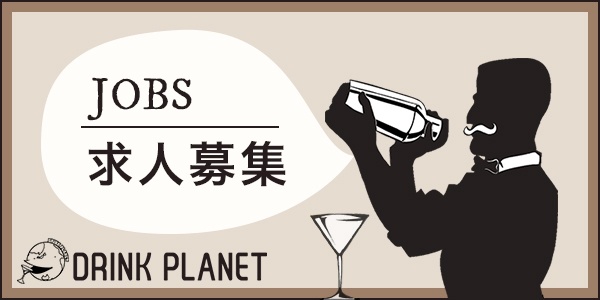SPECIAL FEATURE特別取材
「ディアジオ ワールドクラス 2011」
世界大会レポートfrom New Delhi
[vol.01] -
前編・世界一のバーテンダーになる意味
#Special Feature

大竹氏の優勝の決め手は?
 「マナブがなぜ優勝したかわかるかい?」
「マナブがなぜ優勝したかわかるかい?」
歓喜にわいた授賞式のあと、今大会の審査員のひとりであるバーシーンの重鎮、デール・デグロフ氏が私たちにこっそり教えてくれた。
「それはあのスマイルと、驚きに満ちたカクテル、表現力豊かな楽しいパフォーマンスのおかげだよ。日本人のバーテンダーが技術的に大変優れているのはいまやみんな知っている。だけど足りないものがあった。我々はマナブのようなひとをずっと待っていたんだ!」と。
バーテンダーとしての仕事ぶりが一流であることはもちろん、ゲストに対するおもてなしの心、誰にも真似できないオリジナリティ溢れるカクテル、そして天性ともいえる(?)エンターテイナーとしての才能。
これぞ日本のトップバーテンダー 、マナブ・オータケが、世界に認められた理由なのだ。
デール氏も言っていた通り、会場で出会った世界各国の業界人たちが日本人バーテンダーについて口々に褒め称えるのは、その技の繊細さ、接客の丁寧さ、仕事の速さと正確さ。
いまや日本の優れたバーテンディングは、世界中で高く評価されている。
そして「日本人バーテンダーが作るカクテルの洗練された味の秘密は、彼らが使うバーツールにあるのでは!」と、海外のバーテンダーたちがこぞって日本のツールを手に入れようとするほどだ。
それは日本の文化やMade in Japanの製品が、自分たちのまったく知らないところで外国の人々に愛されていることを知った時のような嬉しい驚きだった。
あまりに皆が同じことを口を揃えて言うので、少しステレオタイプになっている嫌いがあったくらいだったが、大竹氏がそれだけの人ではないことは、誰の目にも明らかだった。
デール氏の言葉は、そんな大竹氏の強みを、ひと言で言い表してくれるものだった。

バーテンダーとしての自分を出し切る。
「ディアジオ ワールドクラス」では、会場での公用語はすべて英語。
世界で勝負したいと考える日本人バーテンダーがまずぶつかる壁だ。
正直、言葉の壁は多かれ少なかれハンデになるのでは、と思っていた。
だが実際に現場を見てみると、通訳付きでの参加が認められているし、競技に関していえば、決して英語がネックになるということはない。
「美味しいお酒を楽しみたい」という気持ちが万国共通であるのと同じで、バーテンダーの仕事にも、国境なんてものはないのかもしれない。
大竹氏について言えば、言葉の違いなどおかまいなしに、自分の持っているものすべてを出し切ったことが評価につながったのではないかと思う。
カタコトの英語でも一生懸命伝えようとすれば相手はわかってくれる。
むしろその姿勢が、共感を呼んだのではないだろうか。
大竹氏の優勝に、言葉がどうのこうのという余計な心配は一気に吹き飛び、同じ日本人として本当に喜ばしく、勇気づけられる思いがした。
この大会では純粋にひとりひとりが「バーテンダー」としての価値を試されているのであって、どこの国出身だとか、どこの協会に属しているだとか、そういったことは決して判断材料にはならない。
必ずしも派手なパフォーマンスを見せればいい訳でもなく、味がよければ結果オーライという訳でもなく、小手先だけの技も通用しない。
審査員たちの厳しい目は、それぞれのバーテンダーが日々カウンターの裏でどんな仕事をしているか、そんなところまでをも見抜いているようだ。
だが「むしろそこに意義を感じる」と、シンガポール代表の日本人バーテンダー江口明弘氏は話してくれた。
それは、彼の仕事に対する自信の表れなのかもしれない。
そして「ディアジオ ワールドクラス」が、真のバーテンダー世界一を決める大会といわれる理由も、そういったところにあるのだろう。


世界一の大会に参加する意味とは?
アジア・パシフィック、ヨーロッパ、中南米、中近東、アフリカという、世界中の32カ国から集まったトップバーテンダーたち。
昼間は張りつめた空気のなかで技を競い合っていた彼らも、夜になればグラスを片手に語り合い、意気投合。
夜な夜な繰り広げられる華やかなイベントやパーティのおかげで、大会が終わる頃にはまるで昔からの仲間のように、すっかり打ち解けていた。(同じバーテンダーだから、話が合わない訳はない!)
誰もがこの場にいられるだけでハッピーだと笑い、お互いの健闘を称え合う。
同じ試練を分かち合った者同士、熱い友情が芽生えていたようだ。
そして今大会では、世界中からなんと約1000人の関係者、メディアが集結。

各国のバーシーンをリードする業界誌やウェブマガジンだけでなく、台湾やブラジルの「GQ」誌、地元インドの新聞やテレビ局、そしてイギリスからは、UK版「料理の鉄人」ともいえる人気料理番組「Master Chef」の取材が入るなど、世界中がこの「ディアジオ ワールドクラス」、そしてそこから生まれる世界一のバーテンダーに大注目。
取材で集まったメディア同士、自分の国のバーやカクテルのトレンドについて情報交換をし合ったり、おすすめのバーを教え合ったり、世界中のリアルな最新情報を得るのにこれ以上の場はないだろう。
選手たちを支えるサポーターや大会を運営するスタッフたちとも、日を追うごとに仲良くなり、交流の輪がどんどん広がっていく。
そして最後には、再会を誓って別れの握手。本当に、いい雰囲気の大会だった。
さすがに世界の大舞台だけあって、大会では技、センス、人柄、どれをとっても素晴らしく「この人がいるバーに行ってみたい!」と思わせるバーテンダーたちにたくさん出会うことができた。
そんなバーテンダーが世界中に増えれば、きっとバーの価値はもっと上がるはずだ。
会場にいたバーテンダーひとりひとりが「Raising The Bar」という大会のコンセプトを背負って立つ存在。
世界一を目指すことはもちろん、そういう思いを共有することが、この大会に参加する大きな意味でもあるのだろう。

総合順位 トップ10
| 1. Manabu Ohtake, Tower's Bar "BELLOVISTO", the CERULEAN TOWER TOKYU HOTEL, Tokyo, Japan |
| 2. Heinz Kaiser, Dino's American Bar, Vienna, Austria |
| 3. Jamie MacDonald, The Raconteur, Edinburgh, Scotland (UK) |
| 4. Torsten Spuhn, Modern Masters Bar, Erfurt, Germany |
| 5. Jimmy Barrat, Zuma, Dubai |
| 6. Tim Philips, The Ivy's Level 6, Sydney, Australia |
| 7. Mickey Lee, Woobar, Seoul, South Korea |
| 8. Aymeric Tortereau, Soda Bar, Lyon, France |
| 9. Ryan Noreiks, Alchemist Cocktail Kitchen, Shanghai, China |
| 10. Mark Huang, Marquee Restaurant and Lounge, Taipei, Taiwan |
続く中編では、審査の対象となる6つのチャレンジを詳細にレポート!
![[Drink Planet] Cocktail portal site for bartenders](/img/common/logo.png)
![[Drink Planet] Cocktail portal site for bartenders](/img/common/logo-l.png)